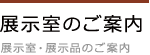2階
総合展示室
県土の誕生[地質分野]
展示品のご案内
琥珀[こはく]

野田村野田玉川/白亜紀・久慈層群玉川層
琥珀(こはく)ときくと、首飾りやブローチ・ネクタイピンなど、素敵なアクセサリーを思い浮かべる方が多いかもしれませんね。
琥珀の色は、いわゆるコハク色だけでなく、緑・青・紅・朱色や、時には金色や銀色の琥珀もあります。重さは割合軽く、濃い塩水に浮かんでしまいます。
岩手県の久慈地方は、国内最大の琥珀の産出地で、良質のものが割合簡単に採集することができます。埋蔵量(まいぞうりょう)も多く、45kgにも達するような大きい塊が産出したこともあります。戦前は、琥珀を燻(いぶ)して虫よけに使っていたそうです。それほど久慈では琥珀が豊富だったのでしょう。
野田村・久慈市・種市町にわたる北上山地の北部・陸中海岸には、白亜紀(はくあき)後期の久慈層群(じそうぐん=9~8千万年前の地層)が分布しています。琥珀は、この久慈層群にたくさん含まれているのです。

琥珀は、樹木から分泌(ぶんぴつ)された樹脂が、幾千万年もの間、土に埋もれ、年月を経てできた樹脂の化石です。樹脂を分泌した樹木は、ナンヨウスギではないかと考えられています。また、樹脂の中には小さな生物も取り込まれることもあり、そのままの姿で残ります。最近(1984~1985年)久慈地方では、恐竜時代《中生代(ちゅうせいだい)白亜紀》の昆虫が、たくさん含まれている琥珀が発見されています。
世界に目をむけてみると、古くから知られるバルト海 沿岸地方産(デンマーク・ポーランド・ドイツ・旧ソ連)のものが有名です。青銅器時代(せいどうきじだい)にはアンバーロード(コハクの道)が開かれました。しかし地質学的年代から見てみると、バルト琥珀は、久慈琥珀より新しい哺乳類時代(ほにゅうるいじだい)《新生代古第三紀(こだいさんき)》にできたものです。恐竜時代に出来て、現在でも採掘(さいくつ)されている琥珀としては、久慈琥珀は世界屈指(せかいくっし)のものです。
ところで久慈の琥珀が人々に利用され始めたのは、縄文時代にさかのぼります。また、聖徳太子第二王子の墳墓(ふんぼ)と考えられている奈良県の竜田御坊山古墳群第3号墳から出土した枕や、島根県の古墳の勾玉(まがたま)も、化学分析により久慈産の琥珀だということがわかりました。遠い都まで運ばれていったのでしょうね。
久慈市小久慈町(こくじちょう)に琥珀博物館があります。そこでは、トカゲ・糸トンボなどの虫入り琥珀や、日本や世界の琥珀 工芸品などが展示されています。久慈の方に足をのばして、訪れてみてはいかがでしょうか。
何千年もかかって自然が作り上げた琥珀は、太古のロマンを感じさせてくれるかもしれませんね。